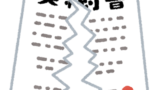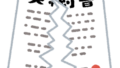前回、購入を申し込んだ築50年の中古戸建ては、残念ながらご縁がありませんでした。
今回はその経験から学んだ、「不動産購入申込書」の記載・提出にまつわる2つのお話しをしたいと思います。
私たちが事前にあまり勉強していなかったため、その場で慌てた内容です。
その内容とは・・・
1 手付金の額を決める
2 住宅ローンの額と金利区分
まず、今回の教訓から得た結論はこちらです。
良かったら、最後までご覧ください。
↓これまでのブログはこちらです↓
手付金の額を決める
手付金は、一般的に購入価格の5%が目安とされています。
私たちの希望額は650万円だったので、32.5万円。
端数を切り上げて35万円に設定しました。
手付金は購入価格に含まれますが、その場で金額設定を求められるとは思っていませんでした。
住宅ローンの額と金利区分を決める
次に決めるのは、住宅ローンの借入額と金利のタイプです。
(1) 住宅ローンの額と借入期間
今回の物件の希望金額である650万円を借りる予定でしたが、不動産会社の方から「住宅ローン審査後は借入金額を増やすことはできません。逆に、審査が通った金額の範囲内であれば減額は可能です。」と説明を受けました。
この話を受け、将来のリフォーム費用も考慮し、希望借入額を予定の650万円から1,000万円に増額することに。
説明は理解はしたものの、その場で350万円も増やすかどうかの選択を迫られるとは想定していませんでした。
さらに、借入期間もその場で決めることに。
具体的な資金計画を立てていなかったので、感覚的な決断になってしまいました。
(2) 住宅ローンの金利区分
住宅ローン審査の過程で、金利区分(固定・変動)まで決めなければいけませんでした。
不動産会社と提携している金融機関のパンフレットを見せてもらい、以下の5つの選択肢が提示されました。
- 変動金利
- 固定金利特約3年
- 固定金利特約5年
- 固定金利特約10年
- 全期間固定
そして、「多くの方は固定金利3年の(●●商品)を選ばれています。あくまで審査に掛けるだけですから」と説明されました。
しかし、その場で「もっと有利な金融機関があるのでは?」「提携先の金融機関だけで決めてしまって良いのか?」という葛藤が…。
結局、担当の方のいわれるがままに「多くの方が選んでいる」という「固定金利3年のローン」を選んでしまいました。
帰宅後、改めて借入利率や今後の金利変動などをシミュレーションし、最終的には提携先の金融機関が一番有利だと判断し、「固定金利10年の(●●商品)」に変更してもらうことにしました。
学んだこと
今回、私たちが勉強不足のまま「不動産購入申込書」を提出しに行ったことで、多くのことをその場で決めなければならない状況に陥りました。
不動産会社の「ダメもとでチャレンジしてみましょう!」という言葉には、「そのあたりの知識はきちんと持っているんでしょ?」というニュアンスも含まれていたのかもしれません。
今回の経験を次に活かすため、今後は最低限、借入金額や期間、そして金利区分を固めてから、具体的な資金計画を立てて臨みたいと思います。
これから不動産購入を考えている皆さんの参考になれば嬉しいです。
それでは今日はここまで🌸
明日も良い日でありますように🌈